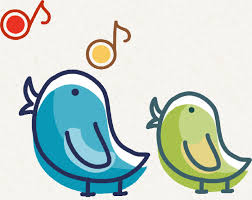NO.1300 わらべうた〝上高田保育園〟年長組 5月

こんばんは
はらやまです
今日は、上高田保育園で
〝わらべうた遊び〟を
行いました
月2回、年長組さんの
預かり保育で約30分間
実施しています
今年度に入って4回目の今日は
台風1号の接近で
一日中雨でした
室内遊びで
エネルギーがあり余っていたのか
とても喜んでくれました
実は、わらべうたの集団遊びは
鬼ごっこを含む
身体遊びです
かなり疲れます
保育士研修会をさせて
頂くと
先生方が、びっくりされるんですよね
〝わらべうた〟は
古くから伝わる
伝承あそびですが
今の子ども達に
まともに役立つ
逆になくてはならない
育ちに必要な武器とも
いえます
(スミマセン 力が入りすぎました)
歌だけではなく
身体遊びの要素が強く
究極のコミュニケーション遊びです
わらべうたの教育力をあげると
他にも
たくさんありますが
コミュニケーション能力を
鍛える遊びとして
みてみると
今、コミュニケーション能力が
低く
友達と遊べない子どもが
増えています
原因は、乳幼児期からの
遊びの絶対量が
少ないからなのだ
そうです
将来、人とうまくやっていく力は
小さい頃からの
遊びで
培われるのです
保育士や子ども同士で
身体を向かい合わせ
共同で遊ぶと
共感力が育まれます
心の響き合う瞬間が
あるのです
〝わらべうたの集団遊び〟は
自分の声を響きとして
感じながら
他者の存在を意識して遊ぶ
コミュニケーションの本質の遊び
であると共に
身体を共鳴させる
遊びです
人類学者の山極壽一先生は
「言葉以外のこういった
〝身体を共鳴させる遊び〟の
コミュニケーションを増やす
ことによって
身体に埋め込まれている
気持や感情を知ることができて
それによって
総合理解が深まる」
と仰っています
そして「私達は今、この戦争が
蔓延しているように
暴力がいろんなところで
起こっている社会を見直して
これまでにはない
アイデンティティの確立を
目指さなければ
ならないと思っているんです」
と続けられています
教育再生のことですね
こういった遊びをしていると
- 自分のできることは積極的にしようとする
- 他者を尊重し、助けが必要な場合は快く応じる
- 丁寧に物事に取り組もうとする
- 話をよく聞き、テキパキと行動する
などの〝育てたい子ども像〟に
近づくような気がして
なりません
*
【2024.5.28 わらべうたの記録】
- 遊戯室に入ると、普段は庭で遊ぶ子ども達が、雨のため大縄跳びで遊んでいた。柱に一方を繋いで保育士が縄を動かしていた。年長になったばかりの子ども達は、大縄跳びに慣れていない。「ゆうびんやさん」「くまさん」を約20分やった。最初、縄を跳越えることがやっとだった子どもが、次第に大回しをする輪の中でも跳べるようになった。わらべうたを指導するポイントはよく見させてマネをさせること。それに大縄跳びはどこに立つかも大事になってくる。担任に立つ場所に印をつけてもらった。歌によってリズムを刻むことも大事だ。「くまさん」の動作に合わせ、子ども達は可愛らしく大縄を跳んだ。初めてなのに2人の子どもができたのにも感心した。他の子ども達も興味深く見ていた。
- 次は、お部屋に移動した。来週から6月なので「ほーたるこい」を計画通りやった。模型の籠に入った蛍を使用した。この役交代遊びは、簡単なルール感覚が学べる遊びである。友達と声を一つにし、保育士とも心を響き合わせながら、信頼関係づくりに役立つ遊びになっている。 蛍の籠でイメージが強く沸いたのか、子ども達の歌声は次第に大きくなり、天の神様の宇宙に届くようだった。次のわらべうたに移ろうとすると、もっと「ほーたるこい」がやりたいと男の子。他の子もやりたいと言ったので、それから6~7分くらい続けて遊んだ。とても楽しそうだった。
- 次に「きーりすちょん」「はないちもんめ」「おちゃをのみにきてください」をやって終わりにした。はないちもんめは、最終的に、女の子がひとりぼっちになってしまったけれど、本人に、遊びをやめるか、それとも一人でもやってみるか尋ねると「がんばってやる」と意欲的に挑戦した。結局最後、女の子がジャンケンに負けて、相手チームに誰もいなくなったところも遊びの面白さだ。一人になったとき泣きそうになる子どもが多い中で、なかなか勇敢な子だと思った。「おちゃをのみにきてください」は、挨拶とトレードを楽しむ遊びになっている。子ども達が必ずといっていいほど笑顔になれる遊びだ。しばらく遊んでから、私が「目を見てあいさつしてる?」とコメントすると、子ども達はハッとして、笑いながら目を見て挨拶をするようになる。とても楽しそうに遊んでいた。
以上で、上高田保育園
今年度4回目の
わらべうた活動日記を
終わりにします
拙文、駄文を最後までお読み頂き
本当に
ありがとうございました
2024.5.28
NO.1298 上高田保育園でわらべうた遊び 豊かな社会をつくるためにわらべうたは良い遊び
こんばんは
はらやまです
今日は、上高田保育園で
年長組さんを中心に
わらべうたの集団遊びを
行いました
月に2回、4:00~4:30の
預かり保育でやらせて
頂いております
あーぶくたった にえたった ♪

今日は、3回目ですが
これから一年間
楽しい〝わらべうた〟を
遊んでいきます
わらべうたの教育力は
たくさんあります
声を一つにして歌い
手足を動かして集団で遊ぶことにより
音楽や情操の教育
仲間意識や連帯感
ルール感覚や
咄嗟の判断力が育ち
ストレスの発散も見込まれます
今日は〝きーりすちょん〟から
スタートしました
簡単な遊びですが
この〝きーりすちょん〟は
わらべうたのなかの
役交代遊びに分類されます
学校教育以前にやっておかなければいけない
ルールをもったもので遊び
役割を自覚して
その通りに遂行しなければいけない
ということが
この〝きーりすちょん〟で
育ちます
来月は〝ほーたるこい〟で
役交代遊びをする予定です
どうぞお楽しみに!
2024/05/15
【過去ブログ】
NO.1290 4月上高田保育園 預かり保育「 年長組の皆さん」とわらべうた遊びを行いました

年長 風組の皆さんと今年も わらべうたの集団遊びが始りました
こんばんは
はらやまです
今日は上高田保育園で
わらべうた遊びを
行いました
預かり保育での
わらべうた遊びです
今年の風組さんも
とても楽しそうに
4:00~30分間
遊んでくれました
帰り際に女の子が
「たのしかった~」と
駆け寄ってくれました
上高田保育園が今年度
初のわらべうたです
喜んでもらえるかなぁ?
少し不安でしたが
これで
ホッとしました
途中、先生方の表情や
子ども達の表情を
確認すると
みんな心から笑っている
感じです
よかった~
ほっ
今年度も
園長先生との話し合いで
毎月2回
昔からやってきた
確かな〝わらべうた〟を
預かり保育で行ってゆく計画です
今年は
『うめとさくら』まで
いけるかなぁ
*
駐車場で
卒園児の女の子に会いました
「わらべうた・・・」
とつぶやいているようです
そばに行って
お母さんに尋ねると
実は、赤ちゃんの頃から
〝朝陽公民館のわらべうた〟
にも通ってくれたのだ
そうです
卒園されましたが
乳幼児期から
年長組まで私のわらべうたに
参加してくれたことになります
やっててよかった~
と思いました
妹さんの迎えにきた
親子さんから頂いた
思わぬ
本日のご褒美でした
2024/04/17
【過去ブログ】
【急上昇 過去ブログ↗】
NO.1273 上高田保育園の預かり保育でわらべうた12月
こんばんは
はらやまです
昨日は、午後4時~
上高田保育園の預かり保育で
わらべうたで遊ぼうを
行いました
年長組の子どもさんを
中心に
自然に2歳児もまじって
楽しい遊びが展開しました
身体を鍛える保育を
しっかり行っている
上高田保育園の子ども達は
ほんとうに体幹がしっかりしています
最初は〝ひらいたひらいた〟で
スタートしました
担任の先生が
ご家族と対応していたので
「じゃあ、そろそろはじめようか~」と
子どもさんだけで
やってもらうと
歌をうたい、手をしっかり繋ぎ
エネルギーがあふれちっています

わらべうたはやっぱり
子ども達の健全な育成のために
なくてはならない宝だな、と
再確認した瞬間でした
「また、来週も来るからね~」と
伝えると
手をたたいて喜んでくれました
【わらべうたで育つもの】
- 仲間関係を発達させる
- 社会生活のルール感覚を育む
- 心身の全体的な発達が促進できる
- エネルギーを自然な形で発散できる
- 体を鍛えることができる
- 感情をコントロールする力を高める
- コミュニケーション力を高める
- 共感性を高める
- 集中力を高める
2023/12/11

NO.1258 上高田保育園の〝わらべうた遊び〟に ご参加ありがとうございました

こんばんは
はらやまです
今日は、上高田保育園で
10時から〝わらべうた遊び〟を
行いました
園庭開放にいらした
親子のみなさんと
わらべうたをたくさん遊びました

わらべうたは
赤ちゃんの
ラジオ体操のようなものです
わらべうたで
やさしく触れ合ったり
くすぐりあったり
抱きしめあったりしながら
子育てを楽しんでくださいね♥
2023/10/04
NO.1248 上高田保育園預かり保育でわらべうたの集団遊び

夕方、4時~30分間
預かり保育で
わらべうたの集団遊びを行いました
月2回のペースで
年間を通して
行っています
今日は、年長の風組さんを中心に
下は1歳の子どもさんも
混じって遊びました
まるくなって手を繋ぎ
- ゆすりゃ ゆすりゃ
- ひらいた ひらいた
- いもにめがでて
- いもむしごろごろ
- てんやのおもち
- ちゃちゃつぼ
- おちゃをのみに
- じゃんけんぽっくりげた
- きーりすちょん
- はないちもんめ
- どっちんかっちん
- とおりゃんせ
- さよならあんころもち
先週宿題にした
茶つぼの両手バージョンが
もうできるようになっていて
大変驚きました
子ども達は
ものすごい速さで
あらゆることを習得してゆきますね
2023/09/05
NO.1244 上高田保育園で集団遊び〝わらべうたで遊ぼう〟

こんばんは
はらやまです
先週は、熱中症アラートが
出て ほんと暑かったですね
早く涼しくなってくれないと
やばいですよ
本当に
さて。夏休みも終わり
また、子ども達のわらべうたが
スタートしました
今日は、上高田保育園の
風組(年長)さんと
16時~約30分間
わらべうたを遊びました
「花いちもんめやりたーい」
「通りゃんせやりたーい」
子ども達は
やっぱりわらべうたが大好きです
途中から、1歳児の赤ちゃんも
年長児にまじって
わらべうたに参加していたのには
驚きました
1歳もやってるよ~
茶つぼの両手バージョンを
宿題にしましたが
難しい手遊びに
取り組むことで
社会脳が活性化
するんですって~
また、来週うかがいます
2023/08/29
NO.1233 上高田保育園預かり保育でわらべうたの集団遊び6月27日

今日は、午後4時~園庭で
〝わらべうた遊び〟をしました
上高田保育園に伺うと
まっ先に
保育士さんがわらべうたの感想を
伝えて下さいました
先生「子ども達は、わらべうたが大好きなんですよ」
私「そうですか~良かった」
いつも、喜々として
遊ぶ子ども達をみて
大好きなんだろうなぁ~と
思っていましたが
直接、様子を聞かせて頂くと
モチベーションも上がるし
大変うれしいです

発達に合った遊びは
時代が変っても
子ども達の心を魅了し続けます
わらべうたは
いつの時代でも
子どもの発達を見据え
チャンスさえあれば
子どもの心をつかんで離しません
子ども達は
ぞうりを履いていました
脱げてしまう子は
途中からハダシです
私の子どもの頃(昭和)を
思い出して懐かしくなりました
祖母のぞうりを突っかけて
遊んでいた、古き良き時代は
足裏の皮膚感覚が
大変身近でした
(たぶん、健康とつながっている)
〝はないちもんめ〟に
夢中になっていると
園庭に作られた田んぼに
落ちそうになって
途中から方向を変えました、笑
(のどかな原風景です)


田んぼには、カエルやオタマジャクシ
ミズスマシがいましたよ
年長(風組)中心ですが
「入れて!」と年中さんも
2歳児さんも混って
遊びが展開されました
2歳児の子が
「ひらいたひらいた」で
輪になって歩き
〝つぼんだ つぼんだ〟の箇所を
歌に合わせて、小さく上手に
足踏みしているのには
大変驚きました
(異年齢の集団遊びの良さですね)
「ああ、楽しかった」「こんどいつくる?」
「きーりすちょん やりたい」
「はないちもんめ やりたい」
子ども達は、わらべうたに 夢中です
2023/06/27
NO.1218 上高田保育園5月〝預かり保育〟でわらべうたの集団遊び

こんばんは
はらやまです
今日も、上高田保育園に伺い
4時~、預かり保育で
わらべうたの集団遊びを行いました
今年度、第3回目です
肉声の歌という音楽に包まれた
空間の中で
子ども達は、今日も
思いきり身体を動かしました
「楽しい?」と尋ねると
「うん、たのしい」という
答えがお約束のように
返ってきます
わらべうた遊びの力です!


NO.1216 上高田保育園の預かり保育で年長組〝わらべうたの集団遊び〟5月
こんばんは
はらやまです
今日は、上高田保育園の
預かり保育で
年長組さん対象に
今年度、2回目の
わらべうたの集団遊びを
行いました
通りゃんせ

「今日は、何からやりたいですか?」
子ども達に尋ねると
「とおりゃんせがやりたい~」
とのことで
♪とおりゃんせ~とおりゃんせ~
と歌をうたいながら
スタートしました
コメントしたことは
- 声を出して歌いながら遊ぶ
- 門をくぐるときに頭があたらないようにする
でした
皆で声を一つにして歌い
手足を動かしてリズムをきざみ
日本の原初的な歌やことばに
触れながら遊ぶことで
音楽や情操の教育ができると
いわれています
本来は、大人が介在しない
ほうが理想的です
ふざけるのも、もちろん
自然の姿です
ふざけている子によって
遊びがダメになったとき
大げさのようですが
挫折感や葛藤、怒りの感情が
体験でき
「じゃあ、こうしよう!」
など、咄嗟の判断力や
気持をたて直す経験にも
つながっていきます
今、仲間意識、連帯感の希薄さが
育成上の課題となっています
体を十分に動かしながら
「楽しかった~」と喜びを分かち合い
顔を見合わせて
気持の良さを一緒に体験することは
仲間意識や連帯感の育ちに
繋がってゆきます

はないちもんめで
残り4人になってしまいました
次は、相手チームの誰を
指名するか相談中です ↓

年長くらいになると
次は、誰を指名するか?
人気のある子にして
エネルギーをもらうか
それとも、ジャンケンの弱い子を
指名して勝つことで
人数を増やすか~
このように、戦略力も磨けます
大切な時期の保育に
ぜひ〝わらべうた遊び〟を
取り入れて
ほしいと思います
次回は、ルール遊びである
わらべうたの
社会性の発達について
書きたいと考えています
2023/05/17
【当ブログおすすめ記事】
NO.1207 上高田保育園 預かり保育で〝わらべうた遊び〟4月

こんばんは
はらやまです
今日は、4:00~4:30
上高田保育園の預かり保育で
年長組を対象に
わらべうたの集団遊びを
行いました
今年度、初めての
わらべうたでした
「きーりすちょん」を
やりたい、と
リクエストがあったので
〝まーるくなーれ〟で
円になってからやりました
子ども達は
うれしそうに笑っています
少子化や核家族化に伴い
帰宅後、子ども達が
同年代の子どもと交流する機会が
少なくなっています
思い切り体を動かして
エネルギーを発散させる効果も
ありますが
友達と遊び
表情や行動、仕草をくり返し
観察することが
わらべうたの集団遊びでできます
これは、今
とても大事な教育と考えられています
調査によると、現代の子ども達は
友達との遊びが少ないので
他人がどう感じているか
人の気持ちになって考える
「共感的配慮」や
対人関係における
「感受性の共感力」が
下がっているのだそうです
これは、たくさんの人と遊んだり
関わって、トレーニングしなければ
身につかなくて
人の気持ちがわからない
若者の増加に歯止めを
かける意味でも
わらべうたの集団遊びを
滅びさせてはいけないと
思うのです
私は、わらべうたの保存活動と
並行して
本来、子どもの遊びであったわらべうたを
子どもの遊びの中に戻し
子どもの伝承に近い形で
根付かせる活動ができたらいいなと
思って、少しずつですが
実践させて頂いております
【ねらい】
- 群れ遊びの絶対量が減ってきている子ども達に、わらべうたの集団遊びを提供し楽しんでもらう
- ルールをもった集団遊びである伝統的なわらべうたで、学校以前にやっておかなければいけない社会性を育む
- わらべうたを皆で声を一つにして唄い、リズムを刻み、表現しながら、日本の原初的な音楽やことばの楽しさを味わう
2023/04/25
NO.1185 第5回 上高田保育園預かり保育でわらべうたの集団遊び2月
こんばんは
はらやまです
今日は、上高田保育園の
預かり保育で午後4時~
〝わらべうた〟を行いました
2月という季節がら
園庭がぬかるんでいましたので
室内で遊んだところ
年少、年中児が年長児にまじって
縦割りの集団遊びになりました

「わたしもやりたい、いれて」
「いいよ」
次々と参加する子ども達の
笑顔はとてもうれしそうです
大切な時期にわらべうたのような
体遊びをすることで
子ども達の何が育つのでしょうか?
手を繋いで「まあるくな~れ」をしたり
「なかなかホイ」で足遊びをしたり
「やなぎのしたには」の手遊びをして
最後には「いろはにこんべいとう」
を元気よく暗誦します
「ひらいたひらいた」と
輪になって
れんげの花がつぼんだとき
必ず笑いが起こります
そのとき、「ああ、子ども達の魂が喜んでいるな」と
思います
わらべうたの教育力は
たくさんありますが
「共感力を育む」ことが
あげられます
皆で遊ぶと 共感力が育つ

わらべうたのような
皆で遊ぶ〝昔遊び〟は
社会脳
コミュニケーション脳が
活性化することが
研究者によりわかっています
調査によると、今若者の間で
共感的配慮や
対人関係における共感力が
下がっていることが
指摘されています
デジタルライフも
関係していますが
辛い状況の人に
共感できる能力が
下がっているというのです
人の気持ちが分らないと
思いやりも生まれないし
平和な世の中にも
繋がっていかないので
子どもの頃に集団で遊び
「共感力を育む」ことを
考え直す時期が来ているのかな
と思います
2023/02/13
おすすめの記事
NO.1158 第4回 上高田保育園預かり保育でわらべうたの集団遊び12月

こんばんは
はらやまです
今日は、上高田保育園の預かり保育で
第4回目のわらべうたの集団遊びを
行いました
朝は、雪がちらついていた天候も
日中には晴れて、午後4時でも
元気に遊ぶことができました
12月も中旬を過ぎた季節の夕方、年長児を中心にわらべうた(集団遊び)をワクワクしながら遊んだ様子をご紹介します。小学校に入るまでに、伝承の教育システムであるわらべうたで遊ぶことは、仲間関係の発達、社会生活のルール感覚、共感性、集中力、感情のコントロール、エネルギーの発散など、この年齢に身につけておきたい様々な発達が期待できます。
【遊びの様子】
4回目の今日は、年中児も自然に入り縦割り保育になりました。総勢25人位の大きな輪になり、どんな展開になるのか検討がつきませんでしたが、中断することなく半ばにさしかかると、ぞうりが脱げたり、靴が脱げたり、鬼に追いかけられて転んだりとハプニングがあって、育ちに良い展開になりました。
期待できるわらべうた遊びの効果のなかで、〝社会生活のルール感覚〝〟があります。つかまったら鬼にならなきゃいけないとか、嫌いな子どもとでも手をつながなきゃいけないということが、わらべうたなどの集団遊びで訓練されるわけです。歌が終わったら、役を誰かに渡しその後釜に入る。役を渡された子どもは、自分の番がきたら役を演じるということがトレーニングされるわけです。
今、子どもの社会性がうまく育たず危機に瀕しているといわれています。小学校以前にやっておかなければいけない子どもの社会化、社会性を育むことができていない。専門家が原因を探っていくと、ルールをもった集団遊びの衰退ということがわかってきたのです。「ルールを持った集団遊び=わらべうたの集団遊び」でもあります。わらべうたは、この時期の子ども達の育ちに貢献してく遊びであったのです。
遊びのなかで、〝あーぶくたった〟の「にえたかどうだかたべてみよう」で、担任の先生が「引っ張りすぎないでね」といいました。普段の遊びでそういう小競り合いがあるのでしょう。私も補足しました。相手の気持ちになって考える〝想像力〟の育ちの場面です。「こうやると髪の毛が引っ張られて痛いよね」「どんな気持ちかな?」質問で子どもに考えさせました。状況を語らせることで、納得してから遊ぶようにしました。〝説得〟じゃなくて〝納得〟しないと、人はどうやら動かないようです、笑。「じゃあ、やってみよう」。効果はありました。が、髪の毛をグシャグシャ適度にやることも遊びの面白みでもあるので、難しいところです。
【感想】
11月からスタートして第4回目が終わりました。担任の先生に「わらべうたを始めてどうですか?」と日頃の様子を尋ねてみました。すると「子ども達はわらべうたをやりたがって、自分達でいつも遊んでいます」とのことでした。やっぱり〝わらべうたは、歴史の選別に耐え、時代をくぐり抜け この令和の時代にもちょっとした隙間から入り込んで 生きていくことができる遊びなんだな と、民族音楽学者 小泉文夫先生のことばを思いだしました。
2022/12/20
NO.1153 第3回 上高田保育園預かり保育で〝わらべうた〟12月


こんばんは
はらやまです
今日は、4:00~4:30
上高田保育園の預かり保育で
年長組を対象に
わらべうたの集団遊びを
行いました
少子化や核家族化に伴い
帰宅後、子ども達が
同年代の子と交流する機会が
少なくなっています
集団遊びを中心に
合計8回の〝わらべうた〟です
本日は第3回目でした
わらべうたは
大変育ちに良い遊びです
近年、わらべうたの教育力が
改めて見直されてきております
【ねらい】
- 群れ遊びの絶対量が減ってきている子ども達に、わらべうたの集団遊びを提供し楽しんでもらう
- ルールをもった集団遊びである伝統的なわらべうたで、学校以前にやっておかなければいけない社会性を育む
- わらべうたを皆で声を一つにして唄い、リズムを刻み、表現しながら、日本の原初的な音楽やことばの楽しさを味わう
【様子】
「はらやまさーん」と園舎から、子ども達が元気一杯かけよって来ました。「わらべうたするものこの指とまれ はーやくしないときっちゃうぞ」とスタート。12月で陽が短いため、時間を前回より30分繰り上げました。天候にめぐまれ、園庭の気温はちょうど良いです。
新しく「きーりすちょん」「やなぎのしたには」「どんぐりころちゃん」を行うと、子ども達は新しい遊びに予想通り興味を示し、くすくすと笑いながら夢中で遊びました。
「やなぎのしたには」は、絵を見せながら紙芝居形式で行いました。やなぎの木の絵を指し「これって何?」と質問すると「やなぎー」と即答。園庭に大きなやなぎの木があるので、もちろん知っていると思ったけれど「ここにもやなぎの木があるけれどどこ?」と聞くと「あそこ」と元気な声が返ってきました。担任の先生からも「もう一度やってもらってもいいですか?」と積極的なリクエストがありました。
【感想】
最後に感想を聞くと、、子ども達は「楽しかった」「面白かった」と元気よく答えました。「また20日に来るから楽しみにしててください」と伝えると「うん!」といいました。
*
わらべうたで遊んでいる姿は
かつての牧歌的な風景を
思いだすようでした
次回も楽しみです
2022/12/12
NO.1150 第2回 上高田保育園預かり保育で〝わらべうた〟11月

こんばんは
はらやまです
今日は、16:30~17:00まで
上高田保育園の預かり保育で
2回目の〝わらべうた〟をしました
対象は、年長児で行いましたが
回を重ねるごとに
縦割り遊びにしてゆく予定です
〝わらべうた〟は歴史の選別に堪え、時代をくぐり抜け 現代に生き残っています。子ども達の魂が喜んでいます

子ども達は本当に楽しそうでした
楽しかったか?
どんな気持ちだったか?
感想をいってもらうと
「楽しかった~!」と
即答です
「また、次も遊ぼうね」というと
うれしそうな顔をしていました
今日は
それまで降っていた雨もやみ
11月末にしては
暖かい日だったので
ラッキーでしたが
次回12月は
もっと陽が短くなって
雪が降るかもしれません
30分早めて行うことにしました
前回から、2週間たちましたが
その間
繰り返し遊んだのでしょう
〝はないちもんめ〟や
〝おてらのおしょさん〟は
すでに
現代の子ども達の手に渡り
『令和の遊び』になっていました
2022/11/29